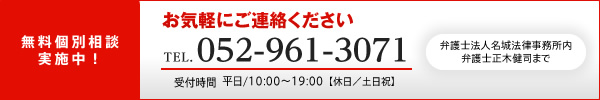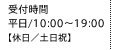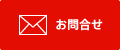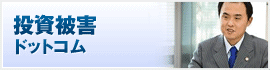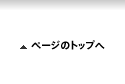個人再生
 |
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残額を原則3年間の分割で支払っていく手続きです。自己破産をすると、借金はなくなりますが、自宅不動産を失います。また、生命保険外交員や会社の取締役などの特定の職業の資格も失います。そこで、破産できない方であっても、借金を大幅に減額でき、自宅不動産を失わず、職業資格も失わないですむ手続きが、個人再生なのです。 |
個人再生の流れ
(1) 弁護士介入通知(受任通知)の発送
受任後、すぐに、全債権者に対し、弁護士介入通知を発送します。この通知には「本人より個人再生手続を受任しました。つきましては、本人に対する一切の取り立てを中止してください。また、以後の連絡は全て弁護士宛にお願いします。」との旨を明記します。これで、債権者からの支払いの督促は全て止まります。同時に、全債権者に対し、取引利益を開示するよう請求します。
(2)申立準備
弁護士が裁判所に提出する申立書を作成します。揃えて頂く必要書類については、最初の打ち合わせの際にご説明いたします。
(3)個人再生申立、裁判官との面談
必要書類が揃い、申立書が出来次第、裁判所に申立てをします。裁判所からの書類通知が弁護士宛に届きますので、全て弁護士の方で対応します。また、裁判官との面談が行われますが、弁護士が同行します。
(4)再生手続開始決定
裁判所が再生手続開始の決定を行い、正式に個人再生手続に入ることとなります。
(5)再生債権の届出
債権者から、債権額等についての届出がなされます。
(6)再生計画案の作成
本人の家計の収支状況を十分に考慮した上で、毎月の返還可能額を決定して再生計画案を策定し、裁判所に提出します。
(7)再生計画案の決議
小規模個人再生においては、再生計画案に対し、反対する債権者が、総債権者の半数に満たず、総債権額の2分の1を超えないことが要件となります。これは、総債権者の異議の有無を書面にて問う方式により、書面決議が行われます。
(8)再生計画の認可決定
裁判所は、債務者から提出された再生計画案につき問題がないと判断すれば、認可の決定を出すことになります。
(9) 再生計画の履行
再生計画認可決定が確定後、その再生計画に従い、分割返済をしていくことになります。
個人再生に関する法律相談については、無料です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。
Q&A
1 個人再生のメリットは何ですか?
個人再生の最大のメリットは、自宅不動産を手放さなくてもすむことです。自己破産では、自宅不動産を手放さなくてはなりませんが、個人再生では、それまで通り住宅ローンを支払いながら、自宅不動産を残すことができます。
次に、借金を大幅に減額できることに加え、原則3年間の分割払いが認められ、将来利息もつかないことです。
さらに、自己破産では、特定の職業(保険外交員や警備員)の資格を失ってしまいますが、個人再生ではこのようなペナルティはありません。また、自己破産では、ギャンブルや浪費の場合には免責されないことがありますが、個人再生ではそのような制限はありません。
2 個人再生のデメリットは何ですか?
貸金業者が加盟している信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、約5~7年程度は新規の借入をすることが難しくなります。
3 個人再生にはどのような種類がありますか?
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生は、主に自営業者を対象とし、給与所得者等再生は、主にサラリーマンを対象としていますが、厳格な区分があるわけではありません。この点、小規模個人再生で再生計画案が認められるためには、これに反対する債権者の数が半数未満で、かつ、その債権額が総額の2分の1以下であることが必要となりますが、給与所得者等再生では不要です。しかし、実際には、再生計画案に反対する債権者は極めて少なく、その一方で、給与取得者等再生では弁済額が小規模個人再生より高額になることが多いため、サラリーマンの方でも小規模個人再生を利用する方が有利であるともいえます。
4 個人再生を利用するための要件は何ですか?
個人再生を利用するためには、以下のような要件が必要となります。
第一に、支払い不能のおそれがあること、すなわち、借金の返済がきわめて困難であることです。
第二に、継続的・反復的に収入を得る見込みがあることです。
第三に、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であることです。
5 個人再生で債務が減額される基準は?
個人再生では、まず住宅ローンとそれ以外の債務(一般再生債権)を分けた上で、住宅ローン以外の債務については大幅に減額することができます。
具体的には、債務額が100万円以上500万円未満の場合は最大100万円まで減額でき、500万円以上1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額でき、1500万円以上3000万円未満の場合は最大300万円まで減額でき、3000万円以上5000万円未満の場合は最大10分の1まで減額できます。
ただし、これら減額した債務額は、債務者の所有財産を清算した場合の金額を下ることはできません。
さらに、給与所得者等再生の場合には、可処分所得要件というものを満たす必要があります。すなわち、債務者の「収入」から最低限度の生活をするのに必要な「費用」を控除した額(可処分所得)の最低2年分を支払うことが必要となるのです。
これらの計算の仕方はやや複雑ですので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
6 住宅ローン特則とは?
住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)とは、個人再生において、住宅ローンの支払方法につき柔軟な対処を認める制度です。例えば、支払いが遅れて期限の利益を失い住宅ローンを一括支払しなくてはならない場合でも、支払計画を立てることで、一括請求を回避することが可能となります。また、一定の場合には、住宅ローン完済までの弁済期間を最長10年間(ただし70歳まで)延長して、毎月の支払いを少額にすることも可能です。ただし、住宅ローン自体の減額は認められず、通常は、それまで通り毎月の住宅ローンを支払っていくことになりますが、これにより、債務整理をしながらも、マイホームを維持することが出来るのです。
個人再生に関する法律相談については、無料です。弁護士が、あなたのご希望を出来る限りお聞きしながら、無理のない解決方法をご提案していきます。まずは、一人で苦しまず、お気軽に弁護士までご相談ください。