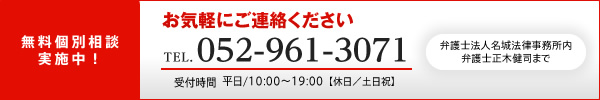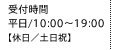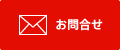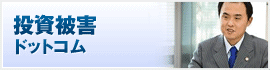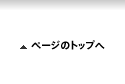管理費滞納の対応策について
昨今、雇用慣行の変化や経済格差の増大等により、マンション管理費等の長期滞納のケースが増えております。マンション管理費・修繕積立金等の長期滞納者に対する対応策としては、以下のようなものが考えられます。
まず、管理組合としては、管理費の支払いを求めて訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行をすることが考えられます。しかし、長期滞納者に預金等の資産が無く、行方不明で勤務先もわからないような場合には、何ら滞納分を回収出来ないどころか、費用倒れになってしまいます。
そして、滞納者のマンションに時価相当額以上の抵当権が設定されている場合には、管理組合としては、住宅ローンの未納等により競売が実行されて正常な新入居者が決定すれば、この新入居者(特定承継人)に対し、これまでの滞納管理費を請求することができます。しかし、競売が行われなければ、管理費等滞納額が益々累積していくことに甘んじなければなりません。しかも、この管理費等は原則として5年で消滅時効にかかってしまうのです。
そこで、管理組合としては、上記判決に基づきマンションの強制競売の申立をすることが考えられますが、当該マンションに時価相当額以上のローンの残債があって管理組合に配当される可能性がなければ、申立は却下されてしまいます(無剰余却下)。
結局のところ、やはり管理組合自身が、長期滞納者のマンションの競売請求ができれば、長期滞納者を強制的に退去させ、正常な新入居者を迎え入れることができ、滞納管理費等も回収出来るようになるといえます。
この点に関し、平成16年5月20日東京高裁決定は、区分所有法(正式名称「建物の区分所有等に関する法律」)59条に基づく競売請求の場合には、上記のような無剰余却下の適用がないことを明確にしました。
これにより、管理組合としては、たとえマンション時価相当額以上のローンを担保するために抵当権設定がなされている場合であっても、上記無剰余却下されることなく、競売を行うことが出来るようになりました。
区分所有法59条は、区分所有者が共同の利益に著しく反する行為を行った場合に、管理組合がその区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるという規定ですが、上記東京高裁決定以前は、いわゆる剰余主義の適用により、その利用の機会は限定されていました。
しかし、今回の東京高裁決定により、長期滞納者対策として、有力な手段となることが期待されます。
なお、同規定を適用するには、「区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によっては共同生活の維持を図ることが困難である」場合に該当すると共に、全区分所有者及び議決権の4分の3以上の特別多数決議、弁明の機会の付与という要件を満たす必要があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
TEL:052-961-3071
名城法律事務所 弁護士正木あて