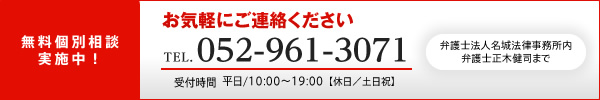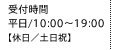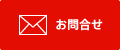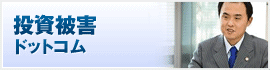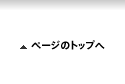懲戒処分について
懲戒処分を適法に行うためには、以下のような要件が必要です。
第一に、就業規則に懲戒事由が明記されていなければなりません。
就業規則に、当該労働者に適用される懲戒事由が具体的に定められていなければ、そもそも懲戒処分を行うことは法的に認められません。その場合、当該労働者に対する懲戒解雇等の効力は無効とならざるをえません。
そして、典型的な懲戒事由としては、①経歴詐称や勤怠不良、②業務命令違反、③職場規律違反、④業務妨害、⑤私生活上の犯罪や非行等が挙げられますが、併せてそれら懲戒規定の内容は合理的なものでなければなりません。なお、懲戒解雇であっても、原則として解雇予告義務があります。
第二に、当該労働者の問題行動の存在が、客観的に証明されなければなりません。
当該問題行動の報告内容が十分に信用できるものか、会社としては客観的かつ中立的な視点をもって、事前に入念な調査を行う必要があります。
第三に、当該労働者の問題行動と懲戒処分の重さが比例していることが必要です。
すなわち、懲戒処分の重さは、規律違反の種類や程度等の事情に照らし、相当なものでなければなりません。
第四に、いきなり重大な処分を与えるのではなく、最初は軽い処分に留めて労働者に改善の機会を付与し、それでも改善されない場合にはじめて、順次より重い処分に移行するべきといえます。
第五に、就業規則や労働協約上、労組との協議や懲戒委員会の討議を経るべき旨定められているときは、当該手続を経なければなりません。
このような定めがない場合でも、処分対象の労働者に対しては、事前に、十分な弁明の機会を与える必要があります。その上で、弁明の機会を労働者に十分に付与したという事実について、書面等で確実に証拠化しておくべきです。(後に裁判等で有力な証拠となります。)
第六に、同一規定に同様に違反した労働者に対しては、平等に懲戒処分規定が適用されなければなりません。
また、従来黙認してきた行為につき懲戒処分を発動するには、事前に十分な警告をする必要があります。
なお、懲戒解雇処分を行った後、場合によっては、労働者が解雇無効を主張して、「労働契約上の権利を有する地位確認」及び「解雇後の未払賃金支払い」の訴訟を起こしてくるというリスクがあります。このようなリスクを回避するためには、急いて懲戒解雇処分を行うのではなく、労働者に自主的に退職願を提出してもらう方が無難であるともいえます。